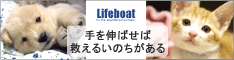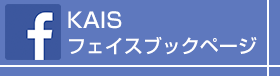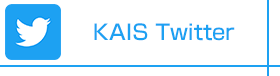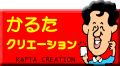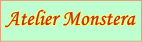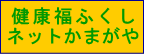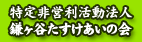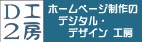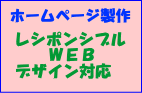-

2024年7月秋田・山形の水害
-
-

2024年7月秋田・山形の堤防決壊箇所
2023年7月23日、アントニオ・グテーレス国連事務総長は記者会見で「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したのです」と、危機感を訴えたのでした。異常気象は、新しい常態になり、灼けつくような暑さ、命を脅かす洪水、暴風雨、干ばつ、猛火に世界中が曝されています。
気象庁の資料では、2024年の気温は世界各地で平年より高く、東アジアでは平年よりかなり高く、特に日本付近で高い気温が記録されています。大阪の3月の月平均気温は13.0℃で平年差+3.1℃。東京の6~8月の3か月平均気温27.0℃で平年差+2.2℃です。こうした高温による熱中症によって7~9月の間で104人の方が亡くなっています。
日本の春(3~5月)、夏(6~8月)、秋(9~11月)の3か月平均気温は、それぞれの季節としては1898年以降で最も高かったのです。こうした状況が続けば、四季の豊かな環境が損なわれ、夏と冬の二季となっていくという声も聞かれます。
異常気象による気温の上昇は、海水温の上昇を招くことになります。これによって大気中の水蒸気量が増大し、局所的なゲリラ豪雨といった異常な降雨による水害や土砂災害といった災害を引き起こします。夏の線状降水帯や冬の線状降雪帯の発生は、くやしいことに、何度でも同じような地域に起こっていきます。
災害を引き起こす異常気象の大きな要因となるのは、やはり「温暖化」ということです。政府や地方自治体、そして企業や家庭生活での対策などが進んでいますが、「パリ協定・気温上昇1.5度以内」達成は、ほぼ無理と予測されています。異常高温や異常降雨がニューノーマルとなった世界が現実のものとなっています。
気象災害をはじめとする自然災害の発生が頻発する状況になってしまっているという現実があります。「災害に強い日本」と言われるためには、電気や水道などのライフラインの復旧が一日も早くできるようにしていくことが求められます。これまでの災害発生でも「災害関連死」が深刻な問題です。避難者への十分な支援ができないままであっては「災害に強い」とは言えません。
未曽有のリスク・不測のリスクにどう備えるかは、大変に難しい問題です。十分な対応計画を作成して、『その時の』ための具体的な方策をし、実際を想定した行動訓練をしていくことなどを関係機関・住民が衆議のうえ備えていくことが大切です。
ところが、実際には「喉元すぎれば・・・」で、そうした意識が薄れていくのが、これまでの現状ではなかったかと思うのです。大きな災害が起きて欲しくないという意識が「正常性のバイアス」となって私たちの行動を阻害してしまうこともあります。 起きるかどうかわからない災害に十分な対策費を充てることは難しい。景気対策や少子化対策など課題は山積みなのですから。予算化し計画的に準備を進めていくことは難しいのですが、災害対策の中心となる市町村の執行状況を注視していくことは必要です。
地球沸騰化による気象災害は激甚化しています。命を守る対策が後手になってはいけないのです。残された時間は少ないのかもしれないのですから。
うむっさん